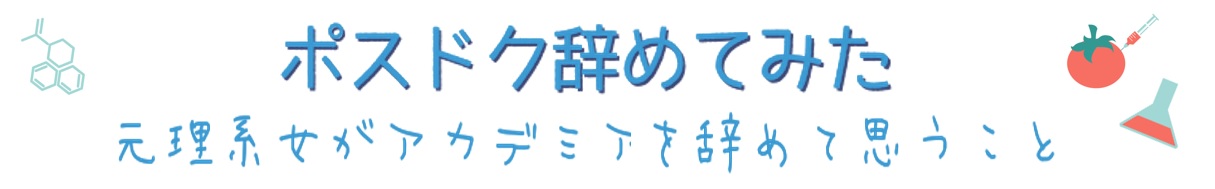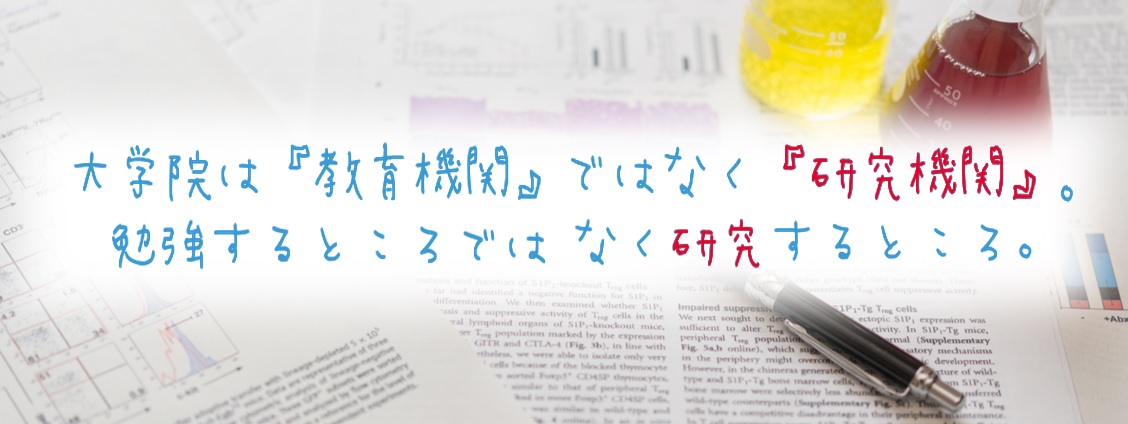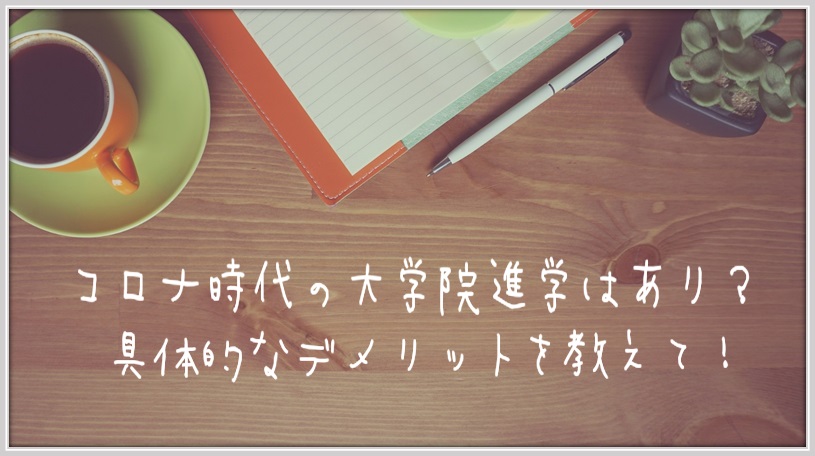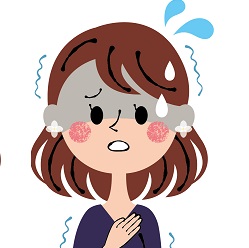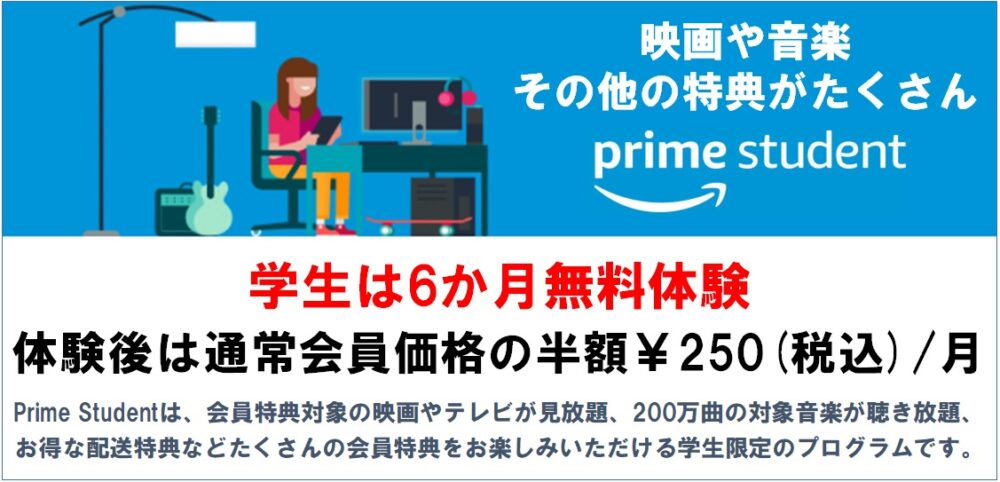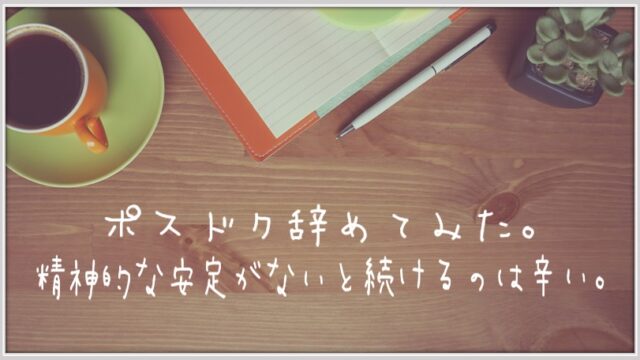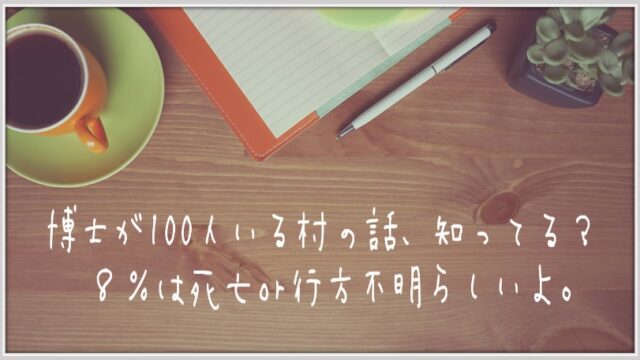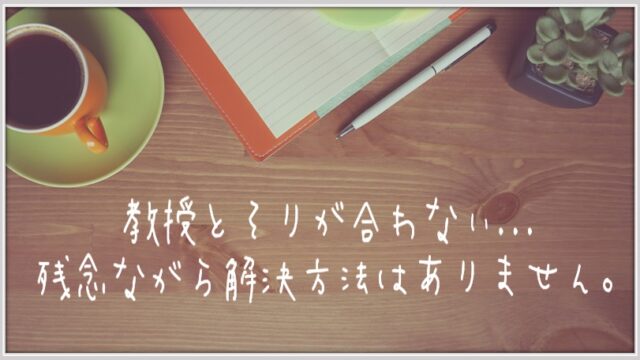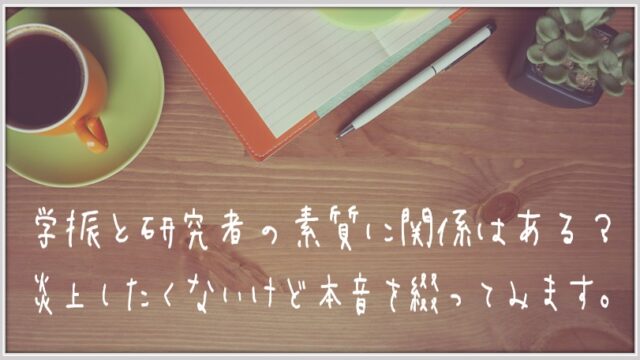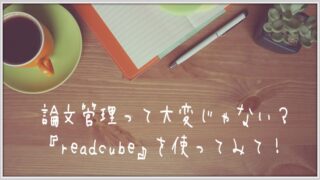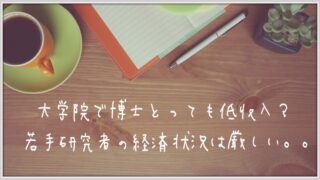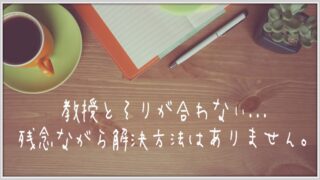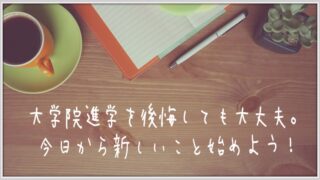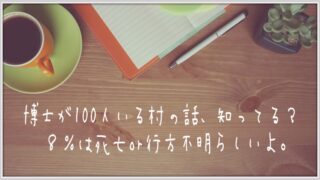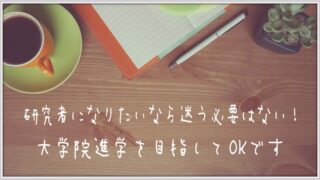- コロナ時代の大学院進学はデメリットが多い。
- 大学院を休学するデメリットはほとんどない。
- 大切なことは大学院で“何ができるのか”を考えること。
本記事では、こんな疑問お答えしようと思います。
ちなみに私は、「コロナの影響で大学施設が使えないのに、授業料がこれまでと一緒っていうのはおかしい!」っと思う派です。
大学側としては「リモート授業への切り替えや経済的に困窮する学生への支援があるため、授業料を引き下げることができない…」という主張があるかもしれません。
しかし、大学施設が機能していなければ電気代は大幅に削減されているはずだし、学生対応する窓口勤務の職員の人件費削減だってできるはず。
要するに、やりようはいくらでもあるはずなのに、学生だけが痛手を食らうってどうなんだろう…とモヤモヤしています。
さて、本題の「2021年度に大学院へ進学すべきか」という問題について。
結論から言うと、「2021年度は大学院へ進学すべきではない」と思っています。
むしろ、2021年度だけではなく、少なくても2022年度までは進学を見送る方がいい。
その理由について、元ポスドクとして大学院に携わってきた側からの見解を解説します。
2021年の大学院進学はちょっと待って!? コロナ時代は学生にとってデメリットが多い
📝大学院進学を辞めた方がいい理由
- コロナによる渡航制限があるため、国際会議・研究会に行くことができない。
- 国内学会・研究会が見送られる(リモート開催)になる可能性がある。
- 経済的な影響が大きい(補助金や給付金などが受けられない)
とはいえ、すでに進学が決まている学生もいるかもしれません。
その場合は、1年間 or 2年間くらい「休学」するこを検討してもいいかも。
※できればコロナが落ち着くまで…。
以下、詳しくチェックしてみます。
大学院進学を辞めた方がいい理由①
国際会議・研究会に行くことができない
大学院に進学するメリットは、研究を通して「価値観」「世界観」が大きく広がることだと思います。
✓研究とは未解決問題を解き明かす試み
どんなマイナーな研究テーマであっても、それは未だ人類が解明していない世界最先端の研究であることは間違いありません。
つまり、研究するフィールドは日本国内で完結することはなく、世界へと広がっています。
しかし、コロナ時代の現在、海外への渡航制限を各国が実施しており、特に島国の日本はその影響をものすごく受けています。
国際会議に参加できない…
国際会議への参加の重要性はこちら:国際会議で痛感した英語の重要性に書いていますので興味ある方はご覧ください。
つまり、「今の時期に大学院へ進学する意味ってあるの?」っと思うのが正直な印象です。
大学院生でなくても、ゼミや研究論文を読むことは、自主的にやれることでもあります。
※休学or進学を遅らせることも選択肢の1つです。
大学院進学を辞めた方がいい理由②
国内学会・研究会が開催されない可能性
2020年度に予定されていた国内学会・研究会の多くはリモートで開催されたようです。
「開催されるだけまし?」かもしれませんが、やっぱり物足りませんよね。。
学会への参加は業績を作るうえでも大切ですが、大学院生の場合は自身研究分野の国内的な立ち位置を把握するためにも学会は重要なイベントです。
✓どのような研究が進んでいるのか。
✓どのような人が同じ研究分野にいるのか。
✓同世代の大学院生はどれくらいのレベルなのか。
学会や研究会を通して、自分の立ち位置を知ることも大切です。
—–Memo—–
研究室によっては一度も学会へ参加することなく修士で卒業していく大学生もいます。
研究に取り組んでいるにも関わらず、学会・研究会へも参加せず、さらには学内で2年間を送って修了するって…。
そんな大学院生は可哀そう…。
研究室、教授に恵まれなかったのかも。
—————–
コロナによる影響で、国内学会・研究会が開催されず、参加実績がないままに大学院を修了しまう可能性・リスクは真面目に考えるべきです。
繰り返しになりますが、大学院に進学するメリットは、研究を通して「価値観」「世界観」が大きく広がることだと思います。
その機会を不運にも奪われたも同然です。
大学院進学を辞めた方がいい理由③
経済的な影響が大きい
従来通りの研究活動ができない可能性があるにもかかわらず、授業料は変わらない。。
さらに研究室で使えるお金(教授の科研費など)も不十分で、間接的に大学院生の研究活動にも影響してくる可能性も考えられます。
「不公平…」っと言うと大袈裟かもしれませんが、そんな感じ。
さらに、仮に修士卒業で就職しても、2023年度の日本経済は不景気真っただ中(もしくは景気下降中…)で若者の先行きも暗い…。
そうした状況も考慮すると、「今の時期に大学院へ進学する意味ってあるの?」ってやっぱり思っちゃいますよね。
少なくても1年 or 2年はタイミングをずらす方が得策ではないか、と思います。
大学院を休学することのデメリットは?【結論:特にない】
休学って聞くと悪いイメージを持つ人も多いと思いますが、実家に帰ってニートして時間を潰そうってことをすすめているわけではありませんよ。
戦略的に時間を有効活用しよう!ってこと。
もし、以下のことを懸念しているのであれば心配する必要はありません。
📝コロナ時代に大学院を休学するデメリット
- 就職する時の印象が悪くなる。
- 奨学金の借入ができなくなる。
- 学費がもったいない…。
考えてみれば納得できることですが、まったく心配しなくでOKです。
簡単に解説します。
休学するデメリット①
就職する時に印象が悪くなる
印象が悪くなる原因は、休学をしたことではなく「なぜ休学したのか」「休学して何をしたのか」という質問に対して、明確な理由を答えられないからです。
例えば「留学していました」っという理由で休学をしていたらどうでしょう。
その結果、英語がペラペラになっていれば超好印象ですが、そうでなければ「留学してなにしてたの?」って思われるかも。
理由がない休学は印象が悪くて当たり前!
さて、2021年に休学する理由は何ですか?
例文を用意しましたので、参考までに。
例1. コロナ時代に大学院を休学する理由
大学院への進学は2020年の時点ですでに決まっていましたが、コロナの影響により大学院で研究活動するメリットを十分に受けることができないと判断し、休学という形をとりつつ教授に相談させてもらいながら個別で研究活動をしていました。
例2. コロナ時代に大学院を休学する理由
修士で卒業することを考えていましたが、コロナ渦による影響により景気が後退し始めたことを考慮し、日本市場全体の景気回復の兆しが期待できるまでは大学院生として社会で即戦力になるスキルを身に着けようと考え休学という形で猶予期間を確保しました。
などなど。
戦略的に考えた結果、「休学を選ぶことが自分にとって最善策だった」っということを説明できれば、印象が悪くなることはありません。むしろ好印象です。
※「学歴に穴が開くと印象が悪い」という考えはもはや時代遅れです。現在はが学歴ではなく“個人の力”が重要視される時代です。
休学するデメリット②
奨学金の借入ができなくなる。
休学中の奨学金についてはこちらをご参照ください。
結論から言えば、休学することを申請すればOKです。休学期間が明ければ貸与は再開されます。
※休学中の貸与は休止状態になります。
なお、博士課程まで進学を考えている方は、第一種奨学金の免除制度についても知っておくといいかもしれません。
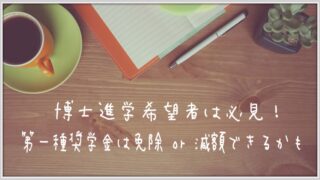
休学するデメリット③
学費がもったいない
「あまり知られていない?」のかもしれませんが、国立大学と私立大学で休学中に必要な学費が異なります。
📝休学中の学費について
- 国立大学
→ 休学中の学費は発生しません。 - 私立大学
→ 年間10~20万円が必要です。
私立大学の場合は、各大学によって異なりますので所属する大学院HPで確認してみてください。
そもそも、現在の大学3年生 or 4年生って休学した方がいいと思いかも?
今の状況で就職活動しても、例年通りに就職先が決まっていくかは微妙ですよね(業種にもよりますが)。
それよりは、1年間ほど休学してその間に社会で即戦力となるスキルを身に着けてから新卒採用で就職活動を再開した方が、メリットは大きいと思いますが、どうなんでしょう…。
最後に:大学院へ進学する目的を明確にしよう!
大学院へ進学するメリットを考えれば、今の時期に進学することはおすすめできません。
📝大学院進学がおすすめできない理由
- コロナによる渡航制限があるため、国際会議・研究会に行くことができない。
- 国内学会・研究会が見送られる(リモート開催)になる可能性がある。
- 経済的な影響が大きい(補助金や給付金などが受けられない)
休学することで新卒時期が1年 or 2年遅れることへの不安を感じている人もいると思いますが、結論からいえばまったく心配する必要ありません。
例えば、大学の同級生の中には浪人生もいたはずです。
そういう人は大学生活の中でなにか不利益を被っていましたか?まったくそんなことないと思います。
しかも、それが1年や2年くらいなら気にする必要はありません。それよりも、もっと悩むべきことがあります。
大学院に進学することで、
✓何ができるのか
✓何をしたいのか
✓何者になれるのか
これ答えられなければ、コロナ渦などに関係なく、そもそも大学院へ行く意味はないかもしれません。
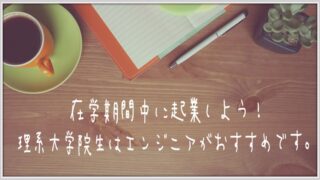
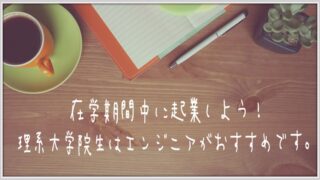
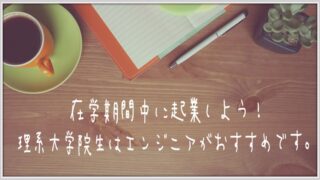
※大学院を休学してスキルを身に着けるのも1つの手段です。