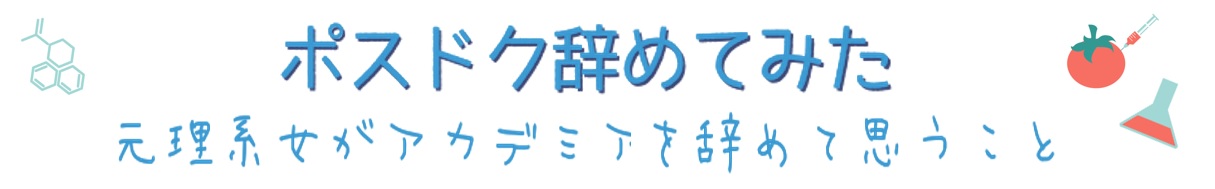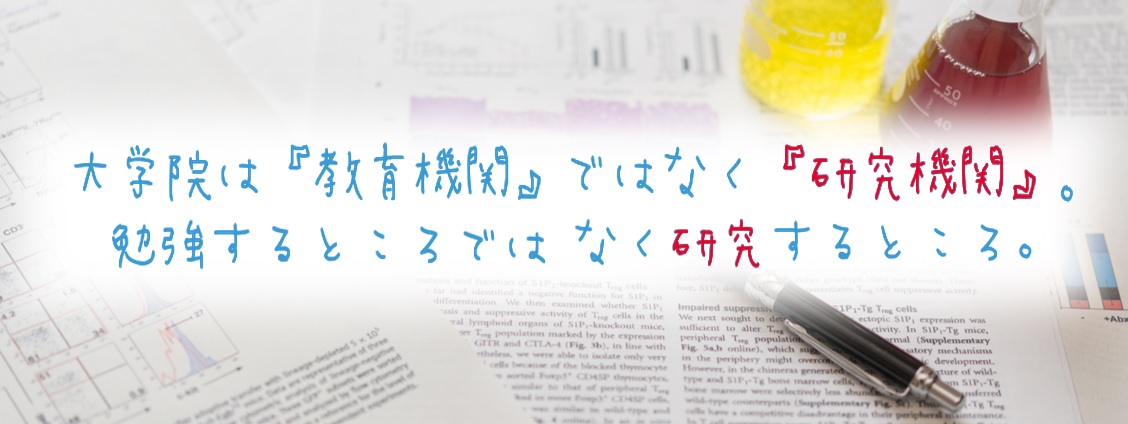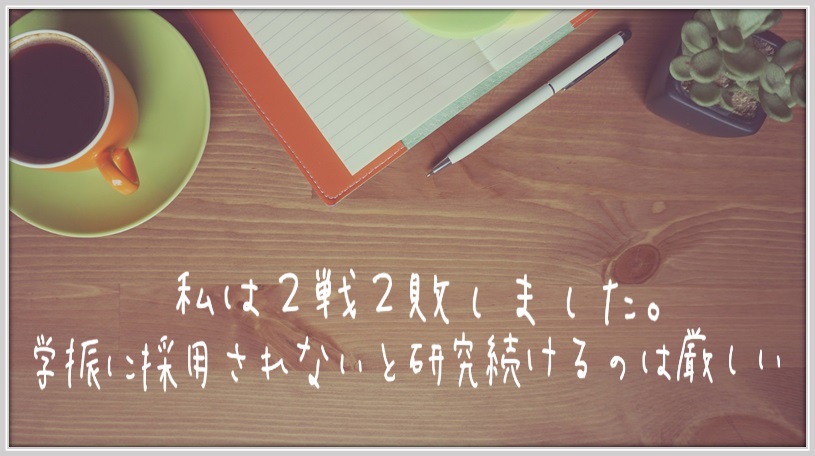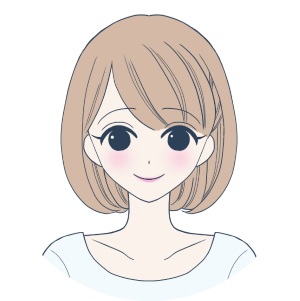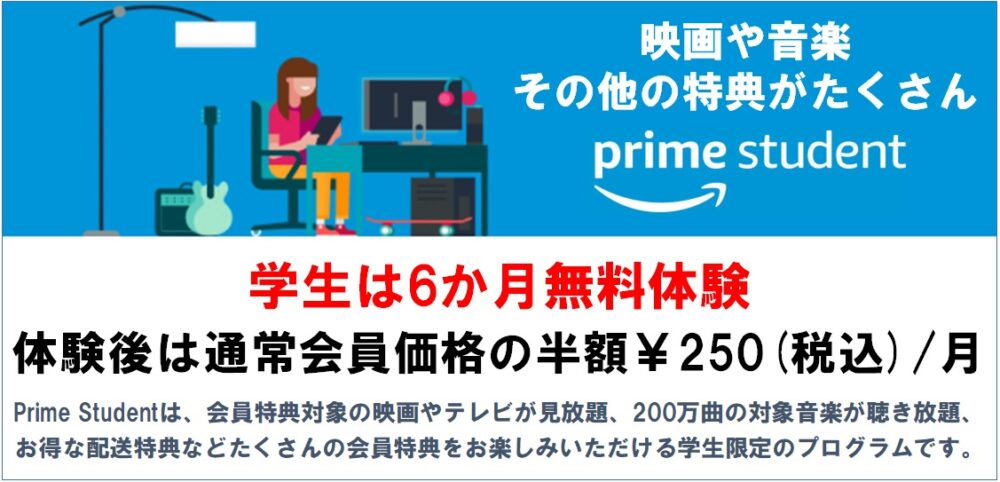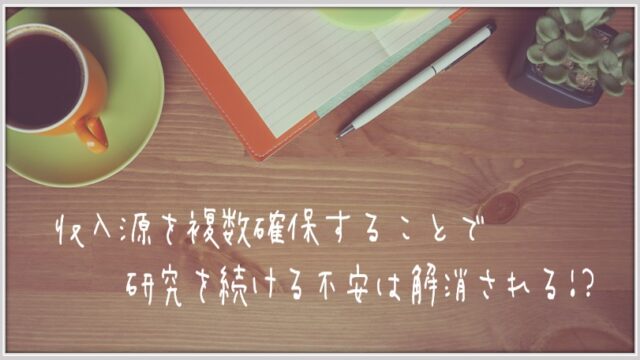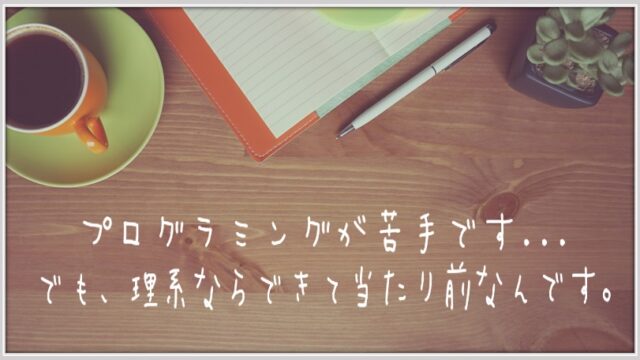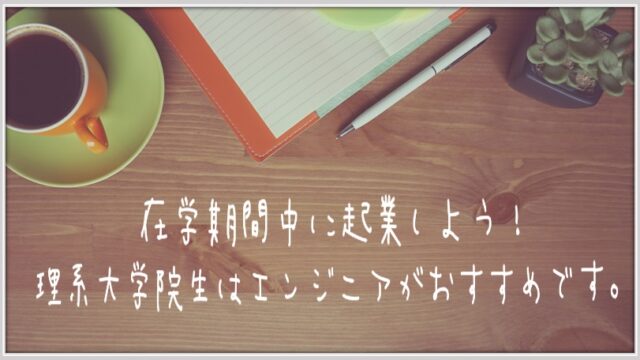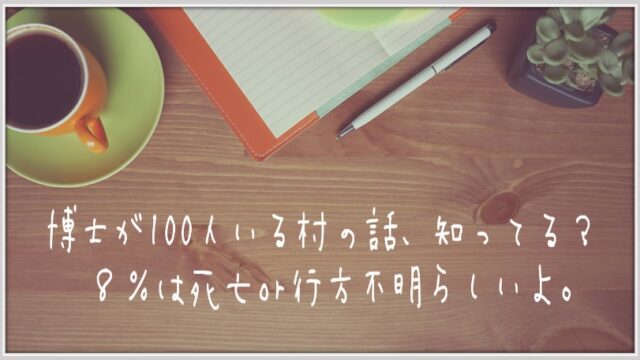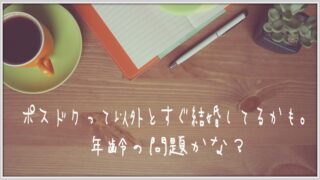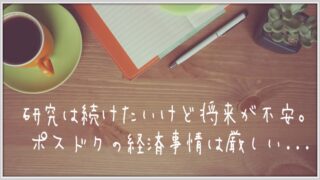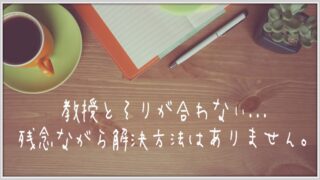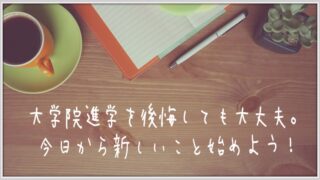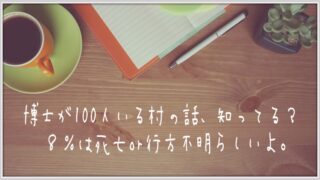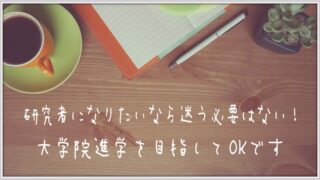学振DC1/DC2に採用されるには論文数が重要。査読付き論文が出ていなければ、学振に採用されるのはほぼほぼ無理。
でも、論文を出せるかは否かは研究テーマ&指導教員次第、というのが現状(だと思います)。
学位取得時の研究成果はざっくり以下のとおり。
- 査読付き論文1本
- 国際会議・研究会:3回参加
- 国内学会・研究会:10回以上参加
ちなみに、大学院博士の頃に2度、DC2に申請していましたが、2度とも不採用でした。
不採用の原因は、学振申請時に論文が1本も出ていなかったことが原因だと思います。
本ページは、学振に通れなかった私の“ひがみ”も含めて「学振とは?学振にさいようれるには?」というお話をさせていただきます。
学振DC1/DC2とは?
まさか、「学振?なにそれ?」っていう大学院生はいませんよね。
学振とは「優秀な博士学生には研究奨励金を支給します」という制度です。つまり、毎月のお給料+研究費がもらえる給付制度のこと。
博士が申請できる学振には、DC1とDC2の2種類あります。
| DC1 | DC2 | |
| 申請時期 | 修士2年次 | 博士課程1,2年次 |
| 採用期間 | 博士課程の3年間 | 博士課程の1~2年間 |
| 奨励金 | 月額20万円+年間150万円の研究費 | |
※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。
※申請条件の詳細は令和5年度(2023年度)採用分募集要項をご確認ください。
月額20万円もらえれば、新卒社会人とほぼ同等尾の給料ですよね。しかも年間150万円の研究費でパソコンなどを買い放題です。
ちなみに、DC1に採用されると、博士課程1年次~3年次まで合計720万円(+450万円の研究費)が支給されます。
とはいえ、もし採用されなかった時のことを想像してみてください。。
自分は学振に採用されずに奨学金を借りて日々極貧生活で研究している一方、同級生は月20万円+年間150万円の研究費でPCやiPadなどを購入し放題。
経済的な不安があると精神的に不安定になりやすく、研究に支障が出ます。本来の実力を発揮できないまま、博士課程3年間を不本意な形でやり過ごしかねません…。
そのため、学振に採用されるか否かで「博士課程での研究生活の命運が決まる」といっても過言ではないでしょう。
※学振に採用されなければ学費&生活費を稼ぐ必要があるため(お金持ちは別)。
とはいえ、経済的なことを言い訳にしても仕方ないので、学振に採用されなければ自分で学費・研究費を稼ぐしかありません。
例えば、理系大学院生なら、Webエンジニアとしてフリーランス起業することも可能だと思います。せっかくなので、学振に採用される以上にすごい博士を目指しましょう。
≫ 大学院在学中にプログラミングスキルを磨きフリーランス起業する方法
※最速かつ確実にWebエンジニアとして働く方法あり!
学振DC1/DC2に採用されるための条件を考察:論文数が重要
学振に採用されるためには、実績となる査読付き論文の数が重要です。論文数によって学振の審査結果が決まると言っても過言ではないでしょう。
しかし、大学院生(博士)が論文を書けているか否かは“指導教員次第”であり、申請者本人の力量だけでは学振に採用されるのは難しいという現状があります。
まぁ、これは私の個人的な意見(指導教員に対するモヤモヤ)なので、学振に採用されなかった“ひがみ”と思って聞いてください。(笑)
だって、論文が出るか否かは指導教員(or 共同研究者)次第ですもんね。。
以下では、私が学振に採用されなかった原因について考察(というか愚痴笑)していますので、参考にしてみてください。
学振DC1/DC2の審査基準
学振の申請書には以下の4つの項目がありますね。
- 現在までの研究状況
- これからの研究計画
- 研究業績
- 自己評価
申請書の中で、最も大きな分量を占めているのが「これからの研究計画」です。
しかし、学振に採用されるか否かの審査に最も影響する項目は「研究業績」です。さらに言えば、査読付き論文数こそが超重要審査基準となっていると言って間違いないでしょう。
つまり、学振に採用されるためには、申請時に査読付き論文が出ていることが条件ということ。
※査読付き論文がない大学院生(博士)で学振に採用されている人を見たことがありません。
おっしゃる通り。。
※大きい声では言えませんが、、研究室(指導教員)によっては学振を見越して自分の研究室のお気に入り学生の業績作りをする教授もいるのです。なぜそんなことするの?と思いますよね。それは… ご想像にお任せします。
とはいえ、研究分野によって論文を作りやすい(短期で論文が書ける)分野と、業績を作り難い(長期でしか論文が書けない)分野があります。
つまり、取り組んでいる研究テーマによって学振に採用されやすい or 採用され難いが決まる、ということは覚えておいていいかもしれません。
学振DC1/DC2に採用されやすい or されにくい分野がある?
以下のように、研究業績が作れるかどうか(査読付き論文が書けるかどうか)は、本人の能力だけではなく、取り組んでいる研究分野によって決まる傾向があります。
✓学振に採用されやすいジャンル
短期スパンで論文が欠けるため申請書に書ける研究実績を作りやすい
- 短期的・突発的な現象の観測や実験を行う分野
- コンピューターシミュレーションによるデータ解析がメインの分野
➡ 1~2年で1本ペースで論文を出せる!
✓学振に採用されにくいジャンル
長期スパンでしか論文が書けないため申請書に書ける研究実績が増えにくい
- 長期的な現象の観測や実験が必要な分野
- 装置開発など、ハードウェア開発を行う分野
➡ 3~5年で1本論文ができるか否か…
もしかしたら今はちょっと傾向が変わっているかな?私が博士課程にいた10年前はこの不公平感を感じで憤っていました。。
※現在は状況が変わっていたら申し訳ございません。
学振DC1/DC2に採用される or されないは指導教員次第?
学振に採用されるには、半年以上前から準備を始める必要があります。
例えば、DC1を狙うのであれば、学部4年生の頃から”査読付き論文”を出すことを意識して研究計画を立てる必要があります。
※DC1の申請時期が修士2年次(5月)のため。
つまり、大学院に入学して13ヶ月以内に、査読付き論文が“Accept”されていなければいけません。
どんなに優秀な修士学生でも、学生の努力でどうこうなる問題ではありません。
そのため、DC1に採用されるためには、指導教員・先輩たちの協力が必要不可欠です。
学振DC1に採用される/されないは研究環境によって決まる?
特に学振DC1に関しては、所属する研究室の雰囲気によって採用されるか否か、もしくは申請できるかどうかが決まると言っても過言ではないでしょう。
もし、以下の条件が揃っているならDC1に申請できる&採用される可能性があると思います。
✓DC1に採用されるための条件
- 大学4年次の卒業研究テーマがサイエンス的に価値がある
- 卒業研究テーマが1年でまとめられる(結果が出る)テーマである
- 指導教員が積極的に面倒を見tくれる、かつレスポンスが早い
- 指導教員以外にも博士やポスドクの先輩が身近にいる
- 英語が得意である
つまり、学振に採用されるだけでも難易度は高いうえに、運の要素も大きいのがDC1です。
上記の条件(環境)が揃っていれば、大学院修士課程の11月頃にギリギリ論文を投稿できるかもしれない…という状況になります。
そのためには、指導教員との相性も大事ですね。
≫ 大学院で研究室の教授(指導教員)と合わない・嫌われた時の対処法
※指導教員とそりが合わなければ最悪です…
※大きい声では言えませんが、、研究室(指導教員)によっては学振を見越して自分の研究室のお気に入り学生の業績作りをする教授もいるのです。それは博士に進学してほしいから。学振に採用されればお金の心配はないため進学を前向きに検討できるため。なぜ進学させたいの?それはその学生が優秀であるため。もしくは… ご想像にお任せします。
もしろん、DC1を申請するために「査読付き論文」が研究業績にあることが必須条件ではありません。
しかし、学振に採用されるためには「査読付き論文」が必須と思って間違いないでしょう。
学振DC2の申請時、論文ないので自己評価でアピッた結果、落ちた…
私は博士1年目と2年目に学振DC2を申請しましたが、2回とも不採用となりました。おそらく不採用の原因は「研究業績」。
つまり、学振申請時に“査読付き論文”が出ていないことが原因だったと思います。
※初めて論文がAcceptされたのは博士3年の10月でした。
申請書をチェックした指導教員に、「この内容で申請書出すの?(笑)」と苦笑されるような自己評価を書いて、いざ申請!
その結果、、
見事に不採用!!(笑)
当然の結果?だし、ダメ元で申請したとはいえ、正直凹みました。。
ちなみに、学振の申請書の自己評価では、以下の2項目について記載します。
✓自己評価に書く項目
- 研究職を志望する動機、目指す研究者像、自己の長所
- 自己評価する上で、特に重油王と思われる事項(特に優れた学業業績、受賞歴、飛び級入学、留学経験、特色ある学外活動など)
私はここでインパクトのあるアイディアとして“カフェの事業計画”を真面目に書きました!
学振には採用されなかったものの、正直に真剣に私の目指す研究者像を書けたので、悔いはありません。今思い返しても、当時の私のモチベーションの高さを感じます。
その内容を一部抜粋すると、以下のような感じ。
目指す研究者像
「研究を通して得られた知識、経験、発見を一般社会に還元できる研究者」これこそが、私が目指す研究者像である。研究成果を論文や学会を通して報告していくことは研究職に従事する者の義務であり、その上で、一般の方々に対して研究を通して得た成果を還元していくことが、研究者としての社会における役割であると考えている。
世界は貧困問題や食糧危機、日本においては少子化問題など、様々な社会問題を真剣に考えなくてはいけない状況の中で、研究者は税金から賄われる有限の財源を使わせてもらっている立場にあり、その感謝と責任を持つべきだと。
実際に研究現場にいると、莫大な資金が使われていことに驚きます。
その財源が国民が納めている税金であることを、研究者は忘れがちです(というか、研究者は意識していない…)。
それは研究者として、とても“愚かだ”と考えていたわけで、「研究者は自身の活動の成果を国民に還元する義務がある!」という主張を申請書を通して誰かに訴えたかったのだと思います。
とはいえ、“想い”だけで学振に採用されるのは難しかったようです。
学振DCは論文がなければ、落ちます。。
まとめ:学振DC1/DC2は論文ないと採用されない!自己評価アピってもダメだった…
大学院博士の頃に2度、DC2に申請していましたが、2度とも不採用でした。
不採用の原因は、投稿論文の研究実績がなかったことが原因だったと思います。
ちなみに、お隣の研究室の学生は1年に1~2本ペースでポンポン論文が出ていました。ほぼ教授が書いてるじゃん?っていう内容でも、first authorは学生の名前で…。
良い悪いの議論は置いといて、これが現実です。
学振に採用される/されないは“論文数”によって決まります。さらに言うと、所属する研究室、研究テーマ、指導教員によって決まると言っても過言ではないでしょう。
以上、博士課程の時に学振に2度申請して2度とも不採用になった元博士のひがみ・愚痴を聞いてくれて感謝いたします。。
結局のところ、経済的余裕が欲しいなら“自分で稼げ”ってことかもしれませんね。大学院生にはWebライターがおすすめです。
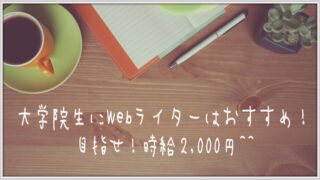
※学振に頼らず自分の力で稼ごう!