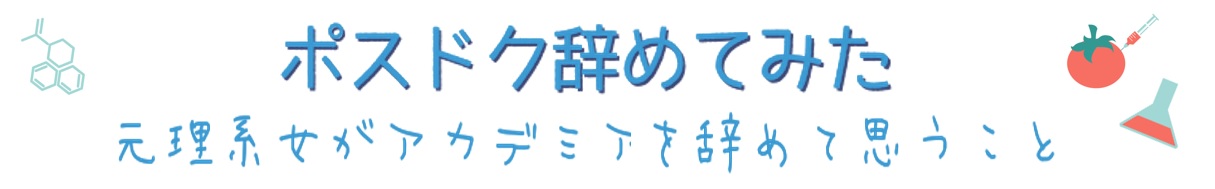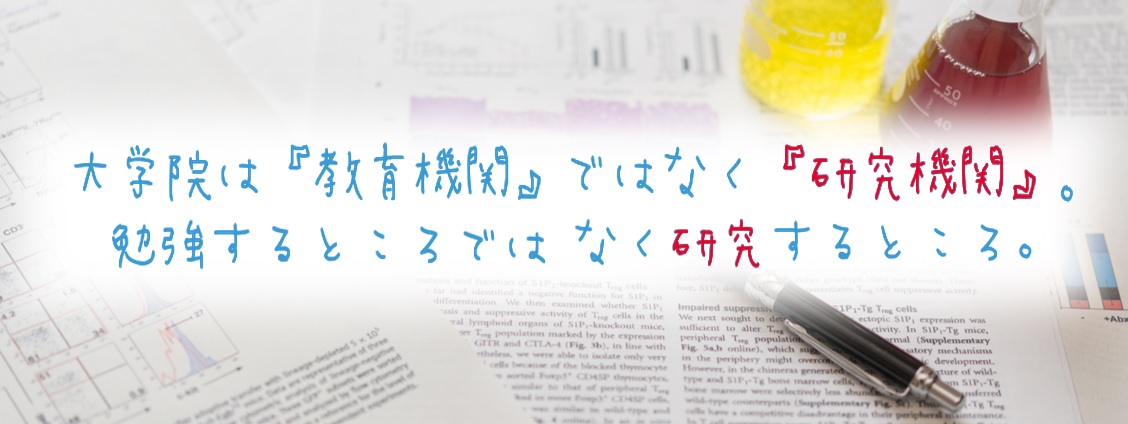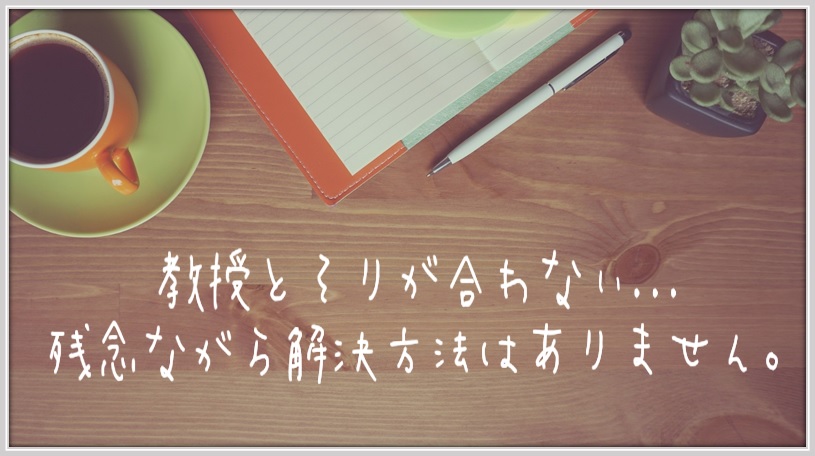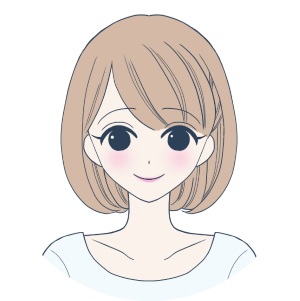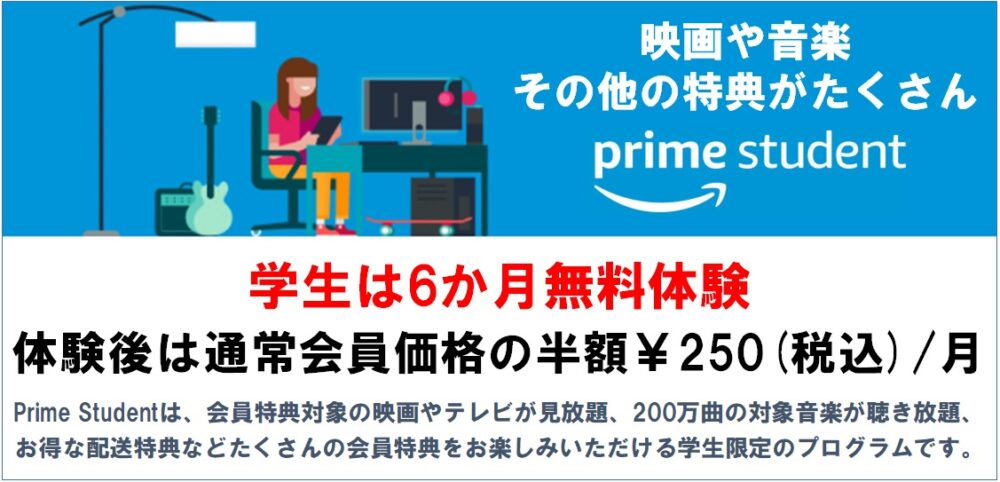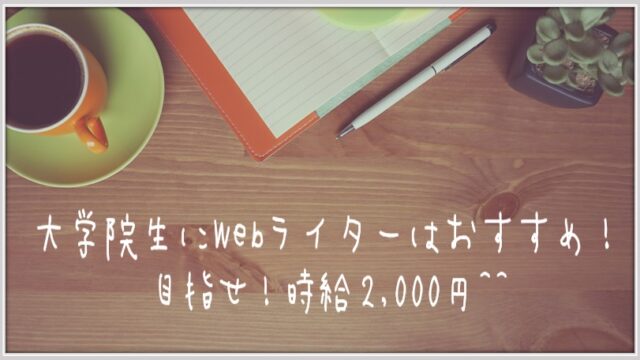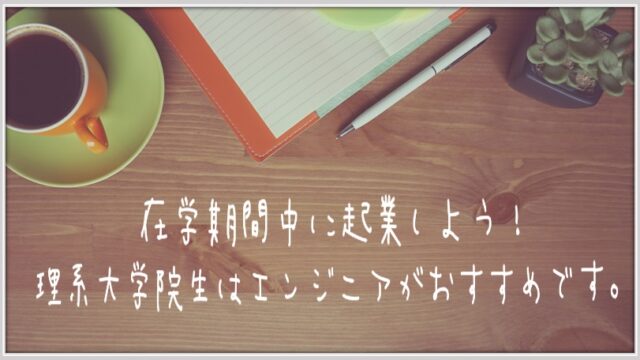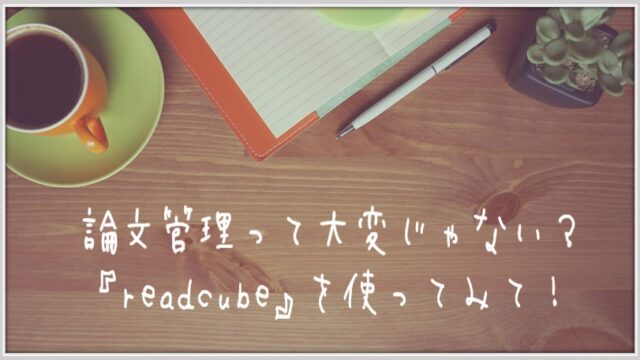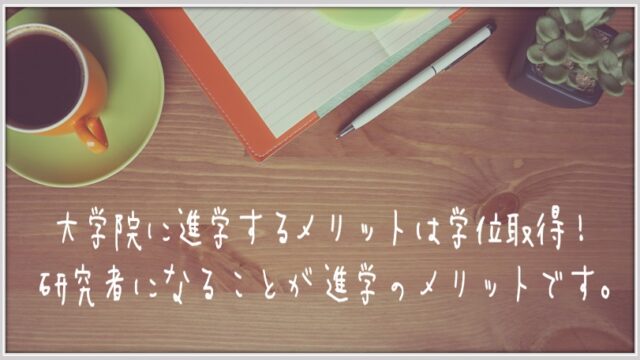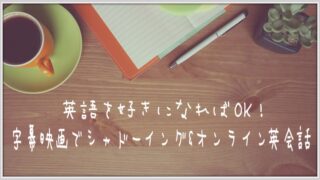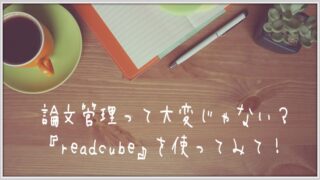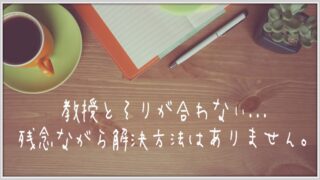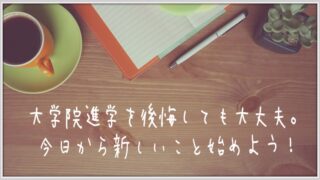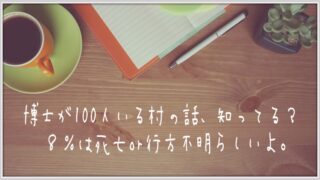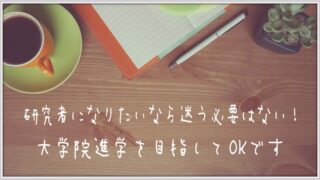教授(指導教員)と上手く付き合えない、嫌われているかもしれない、研究室に行くのが辛い…と感じた場合、研究を辞めちゃってOKです。
※でも退学はしちゃダメ。
あなたには、次の可能性・選択肢があります。
大学院に進学、もしくは4年次の研究室配属後に、教授(指導教員)と合わない・嫌われているかもしれない…と感じることは珍しくありません。
大学院生になると、こういした悩みを抱える学生がちらほら出てきます。
私自身もそうなりかけたことはありますし、後輩にも教授と性格が合わなくて悩んでいる人を見てきました。この状況はどうすれば改善できるのでしょうか。
元大学院生・ポスドクとしての経験を踏まえて結論をお伝えすると、教授(指導教員)と合わない・嫌われた場合の対処法はありません。
とはいえ、大学を辞める必要はありませんよ。
「研究室に顔を出さなくなり、音信不通…。そのまま自主退学…」となることだけは避けてください!
「じゃぁそうすればいいの?」ってことなんですが、元ポスドクの目線から、いくつかご提案させていただこうと思います。
結論からいうと、理系であれば“Webエンジニア”を目指しましょう。
大学院で研究室の教授(指導教員)と合わない・嫌われた場合、研究はやめてOK!
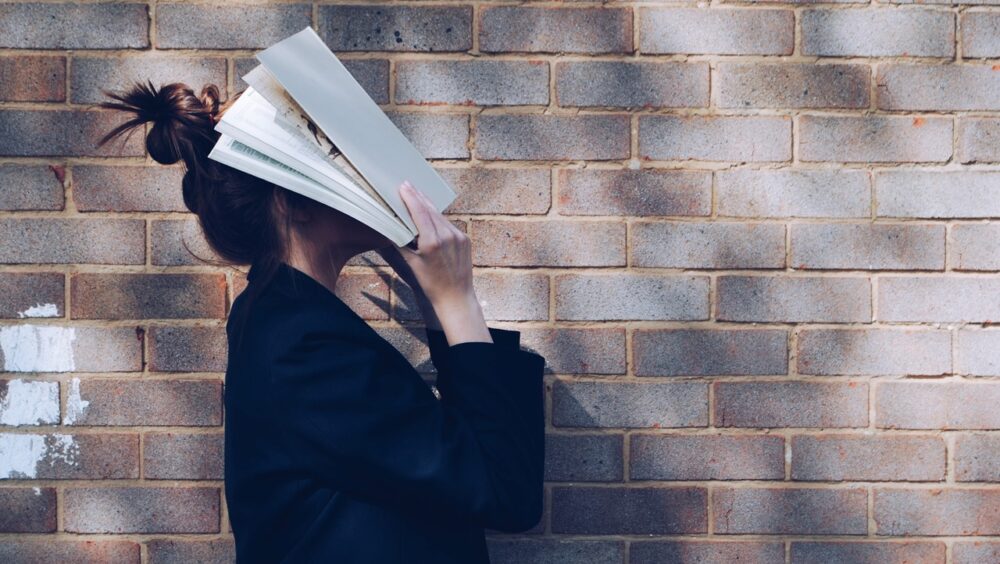
教授との人間関係が原因で研究を続けるのが辛いなら、研究をやめて、大学院在学期間中の時間を自分の将来のために利用しましょう。
確かに。お気持ちはわかります。
でも人生において、すべての努力が実を結ぶことなどありません。1つや2つの挫折や失敗なんて誰にでもあるし、時には将来を見据えた損切りも必要です。
そもそも、大学院という場所に期待し過ぎていたのかもしれません。
大学院は教育機関ではなく『研究機関』です。
残念ながら、研究において学生を平等に指導するといった概念はありませんし、その必要もないかもしれません。
だからこそ、進学前の研究室選びは重要になります。
とはいえ、「それでも研究を続けたい…」という人もいますよね。
でも、少し考えてみて欲しいことがあります。
あなたはなぜ、研究を続けたいと思うのでしょうか?
修士卒の肩書きにほぼ価値はない
修士卒という経歴に拘りたい人もいると思いますが、大卒でも修士卒でも社会的価値に違いはありません。
就職後の出世のことを考えるなら、学歴よりも就職後の実績が重要になります。大卒なのか、修士卒なのかが問われることはないでしょう。
つまり、修士卒にこだわる必要は一切ありません。
ただし、研究職に就きたいなら、大学院後期課程まで進学して博士号を取得する必要があります。そこまでできれば大学院卒(博士卒)の価値が出てくるでしょう。
※例えば理系ポスドクは博士号がなければ就けません。
大学院生が1人で研究を続けるのは無理
論文執筆や学会発表ってカッコいいですよね。学部卒で就職していった友達に自慢したくなりますよね。
でも、どんなに優秀な学生であっても、修士学生が1人で研究成果を出すことは不可能です(論文の書き方も投稿方法もわからないし…)。
研究は発掘作業ではないため、“ポンッ”て研究成果が出てくるようなものではなく、研究背景、研究プロセス、先行研究など、すべてが繋がっているため、大学院生1人で成果を出すのは現実的に無理があります。
つまり、教授(指導教員)の指導・力添えがなければ、修士学生が1人で研究を続けることはできない、ということは事実として受け入れた方が良いでしょう。
残念ですが。。
大学院で教授(指導教員)と合わない・嫌われた後にやるべきこと
研究を続けるのがしんどい…と感じたら、次の3つの選択を考えてみてください。
- 修士卒ではなく学部卒で就職する
- 研究室を変えたいと教授に相談する
- 大学院在学中に起業・フリーランスになる
特におすすめなのが「大学院在学中に起業・フリーランスになる」こと。
履歴書で語れる経歴よりも、個人の実力・実績が重視される社会に変わりつつあるのは確かです。従来の就職活動がオワコンになる時代も近いでしょう。
①:修士卒はなく学部卒で就職する
大学院在学中に就職活動を始めて、就職先が決まれば大学院を自主退学して就職する、ということ。
つまり「就活浪人せずに大学院に進学して履歴書に空白ができるのを回避した」という形に収めてしまう方法です。
ぶっちゃけ、現在の日本は大学院卒が優遇される社会ではありません。
大学院まで進学したのにもったいない気もしますが、結局のところ、大卒であろうと修士卒であろうと就職してしまえば区別されることはないでしょう。
➁:研究室を変えたいと教授に相談する
「研究者を目指したい」もしくは 「どうしても大学院卒の学歴が欲しい」という強い希望がある場合は、正直に教授に相談してみるのが良いでしょう。
実は、大学院って結構融通が効きます。
例えば、A大学院に在学しているけど、B大学院の教授の元で研究をしていて実質的な指導教官はB大学の教授っというケースも珍しいことではありません。
派遣学生的な感じで考えてもらえればOKです。
この場合、そのままB大学の教授の元で修士論文を書いてA大学院に提出して修士号をA大学院で取得、という流れになります。
現在の指導教員に、他大学の研修室を紹介してもらえないか、相談してみましょう。
これくらいは教授も対応してくれると思います。
※もし何も対応してくれないのであれば、そんな研究室を選んだあなた自身にも責任があったと思って諦めたほうがいいかも。
➂:大学院在学中に起業・フリーランスになる
起業といっても「オフィスを借りて従業員を雇って…」というわけではありません。
“フリーランス”として活動できるようにスキルアップしよう!という提案です。
つまり、研究をやめて、大学院在学中に自身の力で稼げる力を身に着けて、大学や就職に依存せずにフリーランスとして働くための準備をしましょう。
もし、大学院在学中にフリーランスという働き方が自分には合わないなっと思えば、新卒で就職するという選択肢もありますよね。
さらに、大学院在学中にフリーランスとして活動した実績がマイナスになることはありません。むしろ、評価される実績になるでしょう。
その他にも、大学院に在籍しておくメリットはあります。
✓退学せずに大学院に残るメリット
- 新卒として就職する選択肢を残せる
- 大学の施設を使うことができる
- 奨学金を利用できる
- 学生起業という肩書が使える
- 国民健康保険、国民年金、住民税などが扶養・免除・猶予にできる
特に奨学金を利用できる、というのは大きなメリットです。
第1種は無利子・無利息、さらに第2種でも銀行などの金融機関から融資を受ける場合に比べると、超低金利で数百万円を借入することができます。これは“学生の特権”と言えるでしょう。
※ただし奨学金を無駄使いしてはダメ。起業資金と思って計画的に使いましょう。
では、具体的に何を始めればいいのでしょうか。
大学院で研究をやめて起業・フリーランスを目指す人がやるべきこと
まず始めに、“何をするか”を考える必要がありますね。
考え方は以下の2通り。
- 自分がやりたいこと・得意なことを仕事にする
- 社会のニーズが高いジャンルを仕事にする
1つずつ見てみましょう。
①:自分がやりたいこと・得意なことを仕事にする
大学院に進学しているあなたなら、すでに何かしらのスキルがあるはずです。
例えば以下のようなスキルに心当たりはありませんか?
✓大学院生が持っているスキル
- プレゼンテーションスキル
- データ分析スキル
- プログラミングスキル
- ライティングスキル
などなど。
具体的に、上記のスキルがどのような仕事に活かせるのか考えてみましょう。
プレゼンテーションスキル
発表するというより、“資料をまとめる”というスキルに着目して欲しいです。つまり、情報をまとめるスキル。
現在、Web業界では、Webコンテンツの情報を図にまとめる図解の需要がめちゃめちゃ高いです。
【図解】新しいアカウントをゼロからスタートして5ヶ月目の収益を公開しました😌
何度も言っているように好きな発信よりも需要がある分野で戦略的に勝負すること。好きな発信は影響力をつけてからであればいくらでもすることができる。まずは需要のある分野で勝負していきましょう✊ pic.twitter.com/9m1Ndr4sjU
— けい I 図解で学ぶインスタ運用 (@keikun_simple) December 26, 2022
「プレゼン資料を作るのが得意」という人は、是非チャレンジしてみてください。
ココナラ![]() などの個人をスキルを販売できるサイトで実績を作れれば、自身のメディアを作ったり、事業化することができそうですね。
などの個人をスキルを販売できるサイトで実績を作れれば、自身のメディアを作ったり、事業化することができそうですね。
データ分析スキル
仮説検証を繰り返すPDCAを回す仕事に、データ分析スキルは必須です。
- P:Plan(計画)
- D:Do(実行)
- C:Check(検証実行)
- A:Action(改善)
PDCAを回す仕事が得意な人は、Webマーケティングに向いています。
例えば、Webサイトの集客方法・効果の分析や商品・サービスのアプローチ、SNSを使ったWeb広告などに活かせます。
プログラミングスキル
理系の大学院生ならプリグラミングできる人がほとんどだと思います。むしろ、プログラミングしたことがない人はいないかもしれませんね。
例えば、Webページの作成やアプリ開発など、プログラミング経験があれば、ググりながら作れる大学院生は多いと思います。
あなた自身は「仕事にできる程のプログラミングスキルは持ってない…」と思っていても、即戦力として活かすことができるケースは多いです。
実際、フリーランスエンジニアを求人募集している案件を見てみましょう。

上の募集案件は、![]() レバテックフリーランスという
レバテックフリーランスという![]() フリーランスエンジニア向けの専門エージェントサイトで募集されている案件です。
フリーランスエンジニア向けの専門エージェントサイトで募集されている案件です。
レバテックフリーランスでは、以下のプログラミング言語の案件を豊富に扱っているため、あなたが得意とする案件が見つかるかもしれませんね。
| 言語 | 雇用形態 | 案件例 | 報酬(月) |
| Java | フルリモート(週5日) | グルメサイト向けエンハンス開発 | ∼1,150,000円 |
| C# | フルリモート(週5日) | 決済システムAPI開発 | ~800,000円 |
| PHP | フルリモート(週3日~) | 音声配信プラットフォーム開発 | ∼800,000円 |
| Rudy | フルリモート(週3日~) | エネルギー比較アプリ開発 | ∼850,000円 |
| AWS | フルリモート(週3日~) | ネットショップサービス開発 | ∼850,000円 |
| Linux | 一部リモート(週5日) | 金融系web/APサーバ公開 | ~700,000円 |
※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。
※引用:https://freelance.levtech.jp/
![]() ≫ レバテックフリーランスの公式サイトを見てみる
≫ レバテックフリーランスの公式サイトを見てみる
※無料登録してあなたに合った案件を探そう!
ライティングスキル
これまでに卒業論文の他、さまざまなレポートを書いてきた経験がありますよね。つまり、大学院生のライティングスキルは人並み以上です。
SEOとは、Search Engine Optimizationの略語です。日本語にすと、“検索エンジン最適化”と訳されます。
つまり、Google検索エンジンで上位表示されるための工夫・施策のこと。Webマーケティングでは、SEO対策やSEOライティングと呼ばれています。
なお、SEOの知識・経験はWebマーケティング全般で必要とされるため、ライティングスキルを磨くことによって様々な職種で通用する人材となるでしょう。
➁:社会のニーズが高いジャンルを仕事にする
自分ができることではなく、社会でニーズが高いジャンルを仕事にすることで、フリーランスとして活動しやすくなります。
例えば、2023年に注目すべきジャンルは次の3つが挙げられます。
✓2023年に注目すべきジャンル
- AI(AIライティング、AI画像生成)
- Web3.0(DeFi, メタバース、NFT)
- 宇宙産業
こうした新しい技術・ジャンルをどのように仕事に活かすかは未知数ですが、ニーズを把握することは可能です。
例えば、クラウドソーシングサイトで募集される仕事を随時チェックすることで、今後ニーズが高まるジャンルを把握することができます。
2020年はYoTubeを始めた人が増えたり、Vlogの知名度が上がったこともあり、クラウドソーシングサイトで動画編集案件が急増しました。まさに、世の中のニーズとクラウドソーシングサイトに掲載される情報がリンクした典型的な例でしょう。
現在(2022年12月)において、AIやNFTなどのキーワードを含む案件が出始めています。これは今後ニーズが高まることを示唆していると言って間違いないでしょう。
まとめ:大学院で研究がしんどくなったら新しいことを始めてみよう!
教授(指導教員)と上手く付き合えない、嫌われているかもしれない、研究室に行くのが辛い…と感じた場合、研究を辞めちゃってOKです。
でも、自主退学はしないでください。
「教授・指導教員に嫌われているかも…」と思う繊細な人は、あまり研究者には向いていないかも。
実際、大学院博士課程に進む人やPDになる人って、良い意味でKW気質な人が多い気がします(偏見かもしれませんが…笑)。
「教授と合わない、研究を続けるのがシンドイ…」と思うなら、無理に関係を修復・改善しようとせず、研究をやめて新しいことを始めましょう。
もやもやした気持ちでいる時間が長いだけ、状況は悪化するかもしれないし、そもそも時間の無駄です。
次にやるべきことを考えましょう。
手っ取り早くできる仕事は、WebライターやWebエンジニア。特に理系の大学院生なら、プログラミングスキルを活かした仕事を始めてみましょう。
![]() ≫ レバテックフリーランスの公式サイトを見てみる
≫ レバテックフリーランスの公式サイトを見てみる
※無料登録してあなたに合った案件を探そう!