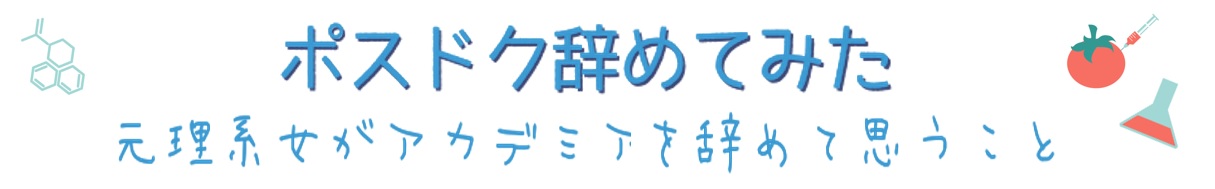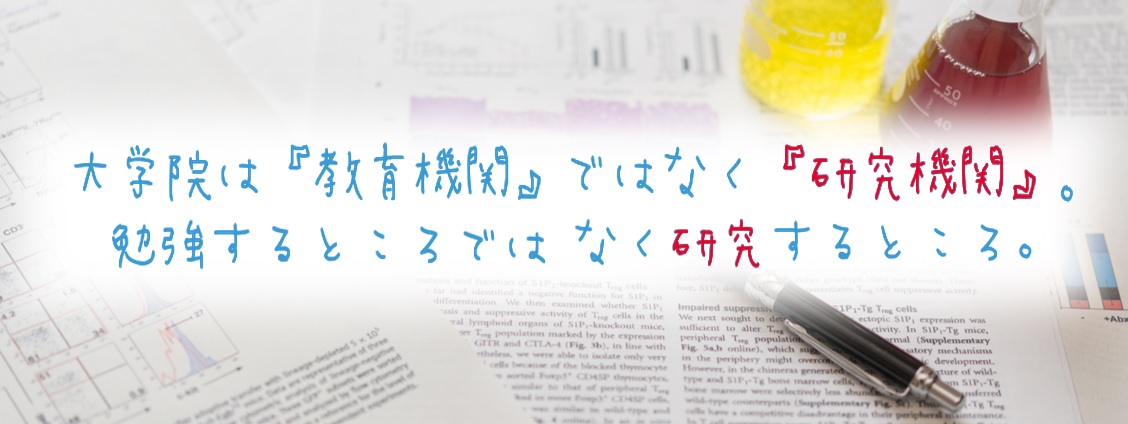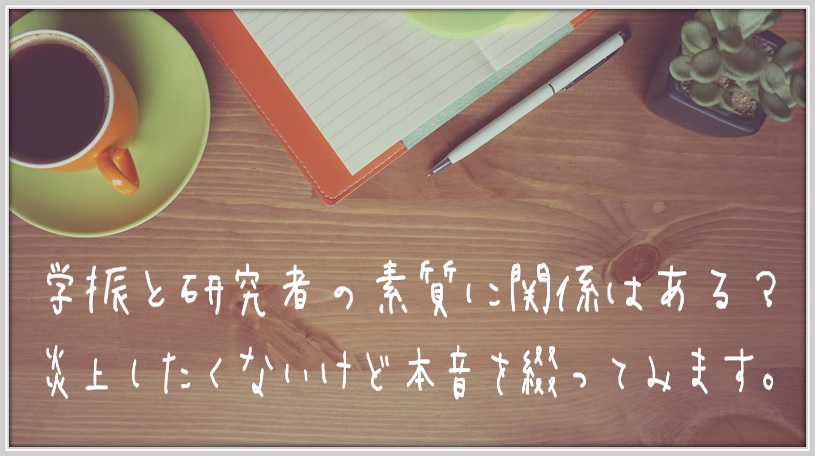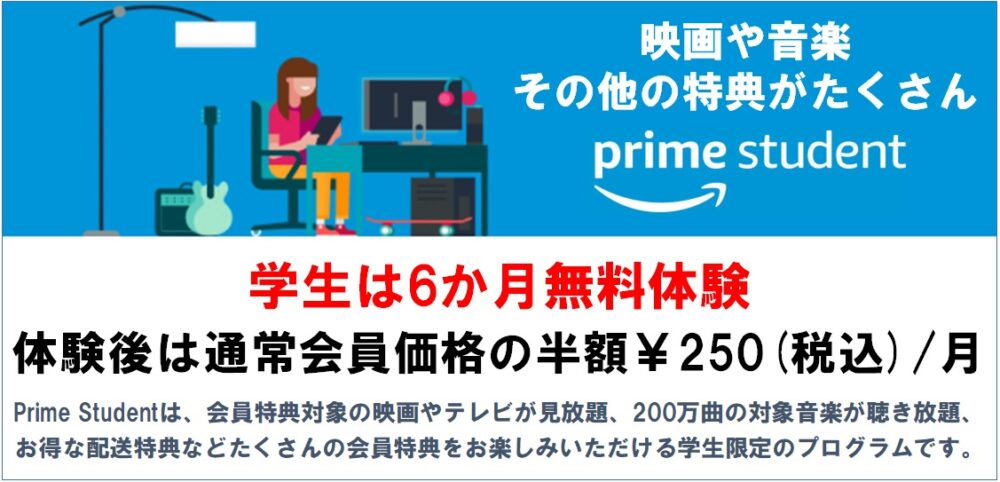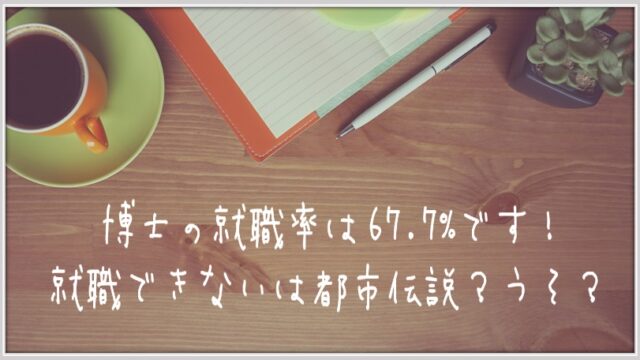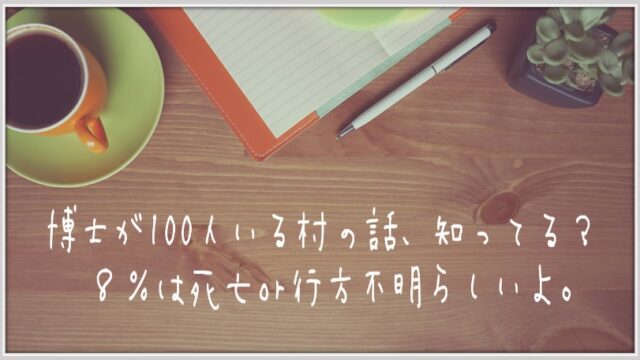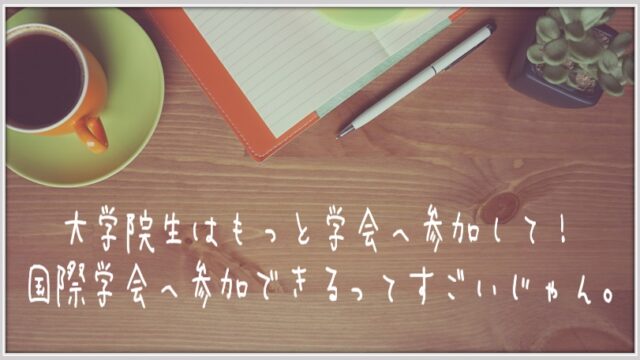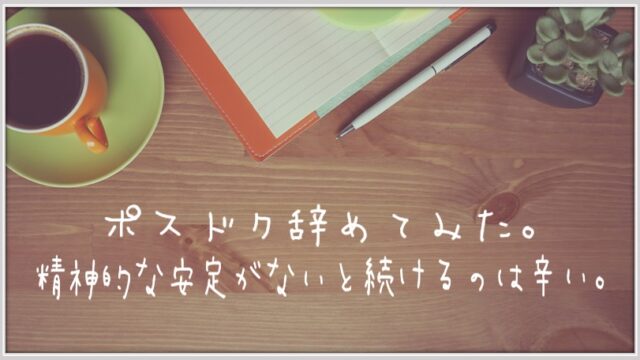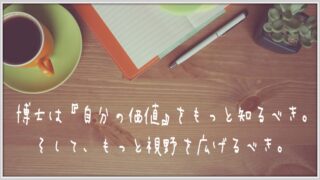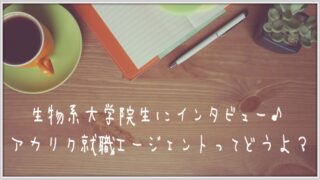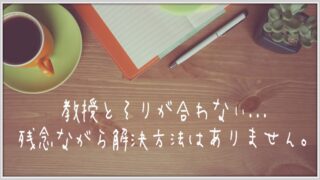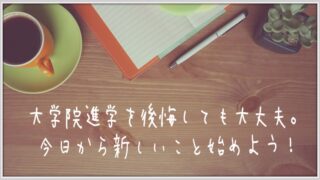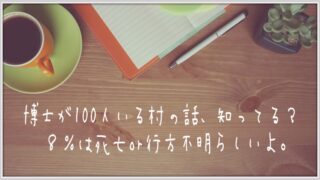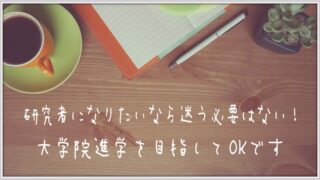元ポスドクの立場から、「学振に採用されない博士は研究者としての素質がない」ということについて考えてみた結果を綴ります。
学振は研究者としての素質を図る指標?
研究者は研究するだけが仕事ではありません。
研究者の人件費、研究費は学振(DC1,2 PD)、科研費、その他から引っ張ってくる必要があり、そのためには、申請書の作成スキルや、時には政治力が必要になることもあります。
こうした“スポンサー”を見つけることができるか否かが、プロとアマの違いになります。
※スポンサーなくして研究は続けることなどできません。
とはいえ、学振に採用されなければ、研究者になれないわけではありません。
誤解を恐れずに言うと、研究者の素質がなくても研究者になることはできますが、そのためには誰かに担いでもらう必要があります。
ポスドクになるにはコネが重要?
でも、指導教員のコネがなければ、間違いなくニートでした。
研究者であれば、研究費を調達してくる仕事は必須です。
それができるか否かは、博士時代に学振DC1,2を取れるかというポイントにおいて、研究者としての素質が問われると思います。
もちろん、学振を取ればければ研究者になれないというわけではありませんし、その後に学振PDや科研費を取ることができないというわけでもありません。
しかし、それは、そこに至る過程において研究者としてのポストを“与えられた”からこその話であり、恵まれた環境にいたからこそ、研究を続けることができたのだと思います。

遅咲きするには、それまでの長い期間に水を与え続けた人たちがいるはずです。
そうした環境がない博士がいるのも事実であり、環境に恵まれなければ自らスポンサーを見つけなくては学位取得後にポストを得ることができません。
つまり、博士の頃に学振を取れるか否かは“研究者”として研究を続けていくための”素質”を図る1つの指標になります。
元ポスドクから重要なアドバイス
大学院で学振DCに採用されなければ、学位を取得できたとしても、指導教員のコネなしに研究職のポストを得ることは難しいかもしれません。
人生は選択の連続です。“就職”という選択も考えておくべきです。

というか、研究者になれるか(ポストを得られるか)って“運”の要素も大きいですよね。
私の場合、学位を取得した次年度が大型の研究プロジェクトがスタートするタイミングと重なっていたために、PDのポストを“運良く”もらうことができました。
もし、そのプロジェクトがなければ(指導教員たちの科研費が採用されていなければ)、研究職に就くことはできませんでしたので。
その他にも、“学振取れない場合は博士課程の学費と生活費はどうすの?”っていう現実的な問題もあります。。
実家が裕福でない限り、学振を取れずに博士課程で研究を続けるのは、ぶっちゃけリスクが高い選択です。。
※本来は、政治がテコ入れすべき問題とも思いますが…。
そのため、“研究を続けられる環境を自分で作ることができるか”という点については、間違いなく研究者の素質が関係しますよね。
研究者の仕事は研究するだけではありません。
自ら研究を続けられる環境を作る必要があり、その第一歩が学振です。
だからこそ、学振に採用されるか否かは、研究者としての素質の有無とは切り離せない問題だと考えています。
※私もポスドクの時に読んでいれば…
以上です。
元PDの一意見として聞き流していただければ幸いです。
※本記事はrikejoblogを参考にさせていただいています。