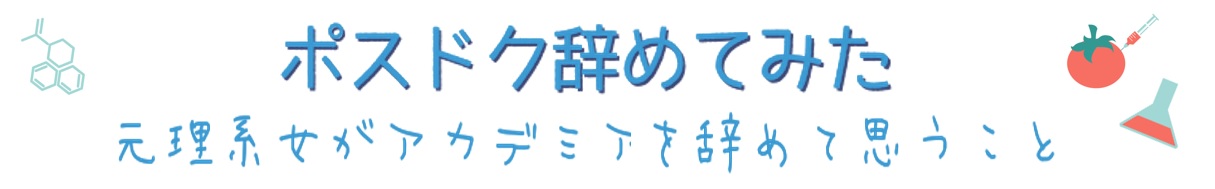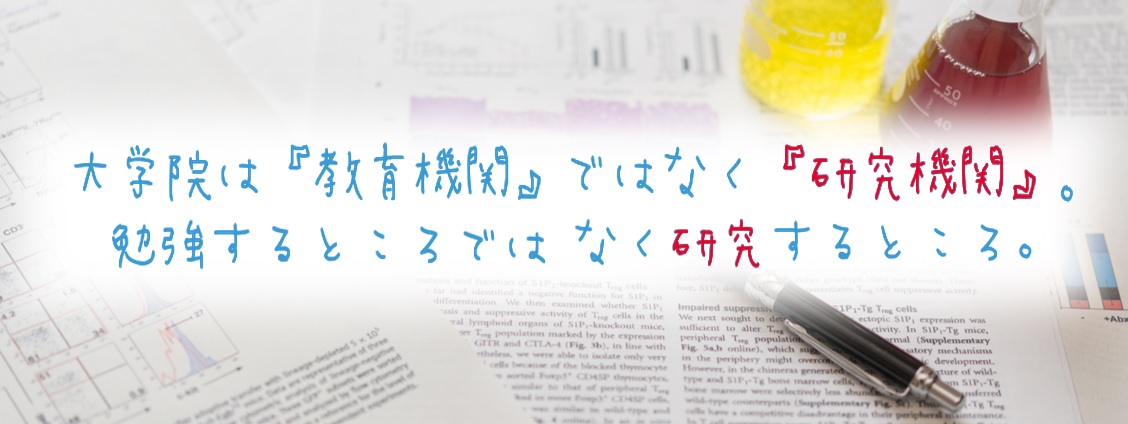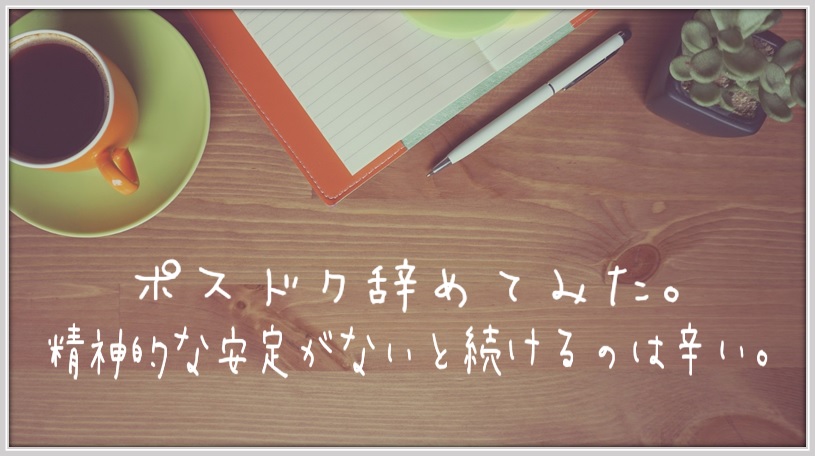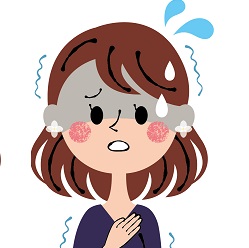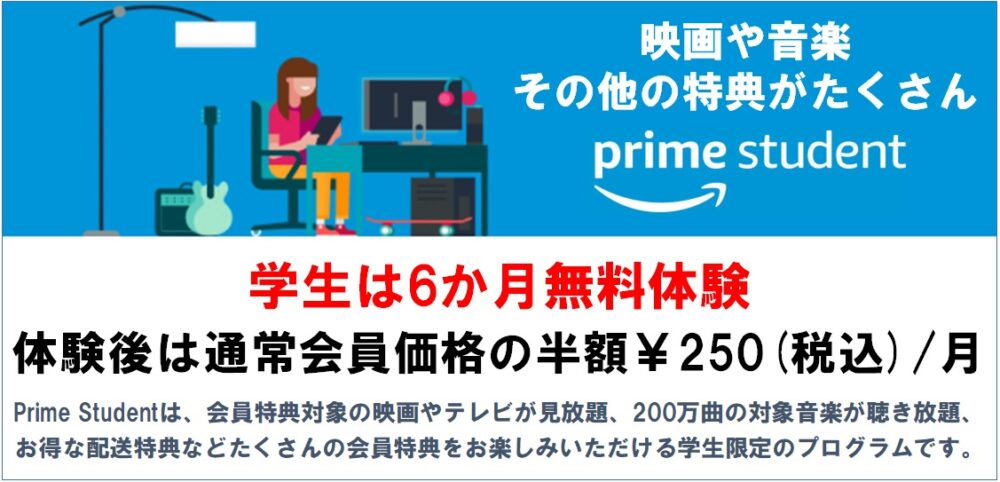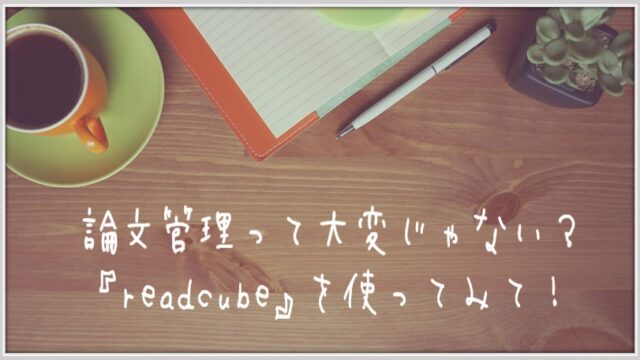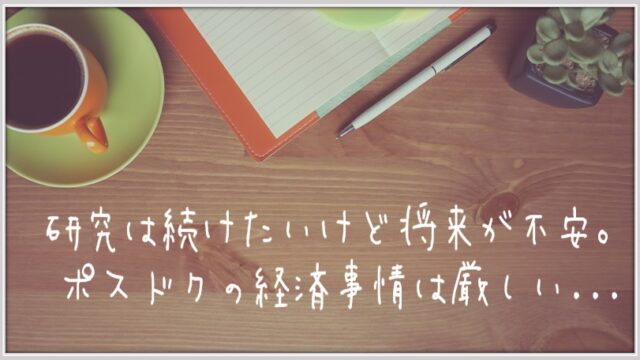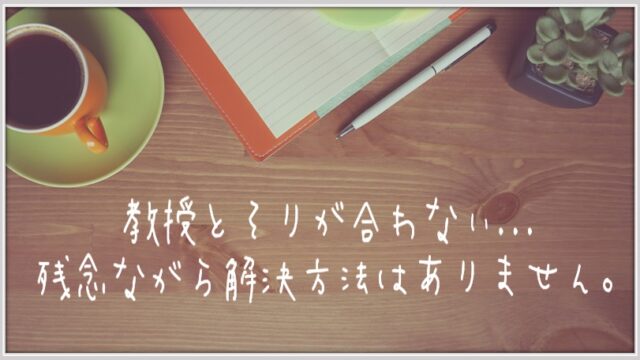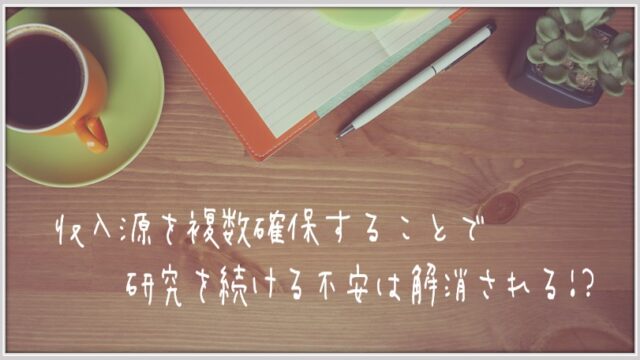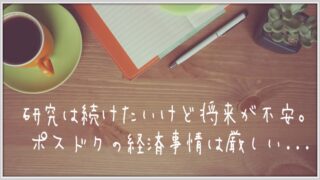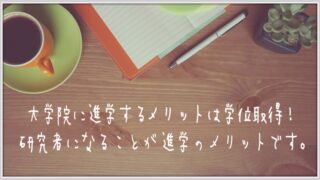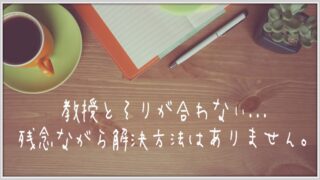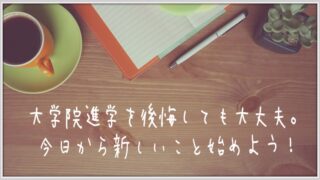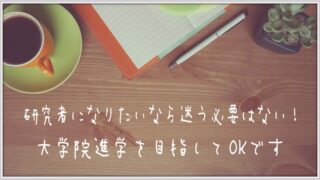- 大学院博士課程で学院を取得しポスドクになった私が研究を辞めた理由。
- 大学院博士・ポスドクを通して得たもの。
- 最後に:博士は研究で培った能力をもっと生かすべき。
私は大学院5年で博士号を取得し、卒業と同時に某大学の研究機関のポスドクとして5年任期で就職することができました。
しかし、ポスドクの2年目で残り3年の任期を残して研究者としてのキャリアに幕を下すことになりました。
大学4年生頃から研究を始めたと考えると、計10年近くの研究活動を続けたことになります。
それにもかかわらず、辞めました。。
本記事では、博士号を取得し、ポスドクのポストも得ていたのになぜ辞めることになったのか、どうしてやめたいと思ったのか、その理由について語りたいと思います。
大学院博士課程で学位を取得しポスドクになった私が研究を辞めたいと思った理由
「やめたい…」というネガティブな気持ちが日々増していき、さまざまな要因が重なった結果、総合的に考えて辞める決断をしました。
※当時は冷静な判断ができない状況だったかも。
結論から言うと、「私は自分に与えられた研究環境に甘えていただけ」だったかもしれません。
とはいえ、当時は必死でした。
なかなか目に見えた成果を出すことができず、周りの優秀な同期のポスドクに劣等感を感じながら、自分の不甲斐なさに失望しつつも、自分なりに頑張っていた“つもり”でした。
今になって冷静に考えれば、あの時の私は“休むべき”だったと思います。
📝私が研究を辞めた理由
- 研究に社会的価値を見出せなくなった。
- 経済的に将来が不安になった。
- 自己成長に限界を感じ始めた。
大学院生やポスドクの方であれば、こうした不安と日々葛藤している人も多いと思います。
それとは対照的に、こうした不安を感じながらも「まぁそんなこと考えても仕方ないしな」と割り切っている(or あまり考えていない?)人もいます。
繊細な人は研究者に向いていない!?
このページを訪れたあなたが、大学院生もしくはポスドクであれば、すでに不安を感じている証拠ですよね。
もしかすると研究者に向いていない性格かもしれません。
さて、私が研究職を辞めた理由についてもう少し掘り下げてお話します。
研究を辞めた理由①
研究に社会的価値を見出せなくなった
“社会的価値”なんて考えている時点で、研究者に向いていなかったのかもしれません。
~余談~
2002年にノーベル物理学賞を受賞した東京大学の小柴昌俊先生は、「その成果は将来、何かの役にたつのでしょうか」という質問に対し、「まったく役立たない」と答えたことが話題になりました。
大学院博士課程にいたころは、私なりの「研究者とはこうあるべきだ」といった信念に近い思いがあり、日々研究活動に没頭していました。
その思いが、自分自身の重荷になっていたかもしれません。
📝私が目指した研究者像
「研究を通して得られた知識、経験、発見を一般社会に還元できる研究者」これこそが、私が目指す研究者像である。研究成果を論文や学会を通して報告していくことは研究職に従事する者の義務であり、その上で、一般の方々に対して研究を通して得た成果を還元していくことが、研究者としての社会における役割であると考えている。
しかし、博士号を取得しポスドクとして研究プロジェクトに所属し、チームで研究を進めていく中で、こうした私の想いは徐々に薄れていきました。
その結果、取り組んでいる研究プロジェクトに対する社会的価値を見出せなくなった結果、「なんのために私は研究しているのだろう…」と、答えのない問いを自問自答し、自暴自棄になるばかり。。
社会的価値を見出せなくなった大きな原因は、私が所属するプロジェクトの運営実態に疑問を感じたことがきっかけになり、さらに、本研究プロジェクトに当てられた莫大な研究資金が、税金の無駄使いとしか思えなくなったたためでした。
✓プロジェクトの研究費:5億円
とはいえ、研究プロジェクト自体の意義や価値は高かったと思います。
しかし、それは研究プロジェクトの表向きの見せ方であり、その運営状況は5億円もの予算が組まれているものとは思えないほどのものでした…。
※当時の私の視野が狭かっただけの可能性もありますが。
研究者によっては「5億円のプロジェクトなんて大したことない」「それくらいの研究規模のプロジェクトはありふれている」と言う人もいるはずです。
しかし、そうした意見がでる時点で、ちょっとおかしい。。
同時期くらいに、ある研究機関が問題になり、研究室用の椅子が一脚20万円といったことでも、研究費の使われ方が話題になりました。。
研究を辞めた理由②
経済的に将来が不安になった
研究職に就くためには大学院博士課程にまで進学し、そこで学位を取得する必要しなければなりません。
※理系分野ならこれが必須条件です。
つまり、研究者になるためには最短でも27歳までは学生という立場になります。
それまでには当然学費も必要になるため、若手研究者は経済的に大きな負担を背負うことは避けられません。
学振に採用されるか、実家が裕福でない限り、奨学金を借りざるを得ない状況になります。
学振に採用されないと経済的に苦しい…
大学院時代に学振DCに採用されなければ、その後はイバラの道が続きます。
経済的に苦しい状況から抜け出すことはできず、さらに指導教員のコネがなければ、研究職のポストを得ることもかなり難しくなります。
ちなみに、私が学振に採用されることができなかったため、奨学金を借りて生活費、学費を工面していました。。
※今思えば、学振に採用されなかった時点で、研究者のキャリアを捨てるべきだったと思います。
ポスドクの給料:総支給360万円
もしろん、交通費な残業代、ボーナスなどは一切ありません。
月々の手取りはもろもろ引かれて25万円ほど。
そして、月々の生活費の内訳は以下の通り。
ポスドク時代の生活費
- 家賃:52,000円
- 水・光熱費:15,000円
- 電話代:10,000円
- 食費:30,000円
- 交際費:20,000円
- 奨学金返済:55,000円
⇒ 合計:182,000円
正直いうと、手取り25万円あれば、奨学金の返済で毎月55,000円引かれても、まったく生活できないレベルではありません。
しかし、知人の結婚式や実家に帰省するための旅費などの出費があった月はギリギリですし、特に贅沢をしたかったわけでもありませんが、生活水準は大学生の頃のまま。
というか、社会人1年目から毎月55,000円の返済を抱えるって普通ありえませんよね…。
恒産なくして恒心なし…
さらに、この時は任期5年のポスドクだったため、この任期がきれた途端に無職になる可能性も考えておかなくてはいけません。
仮に、任期終了後に別のポストへ移ることができたとしても、現在の給料が維持されるとは限りません(むしろ下がる可能性だって普通にありますから)。
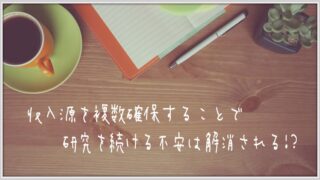
※研究者になっても給料は期待してはいけません…
研究を辞めた理由③
自己成長の限界を感じ始めた
当時の精神状態は“鬱”でした。。
今振り返れば、そんな状態で研究を続けること自体が無理だったんだと思います…。
✓研究に集中できない…
✓作業効率が極端に落ちている…
✓1日でできた仕事が1週間かけても終わらない…
頑張ろうとすればするほど、状況は悪化していきました。
研究実績や経験を重ねることで、自分の成長スピードを実感し、自らの研究者としての可能性は広がり続けるということを確信して疑うこともありませんでした。
そう思っていたからこそ、奨学金の借入さえ将来の投資だと思い躊躇しなかったんです。
まさか、その数年後に“鬱”状態に陥ってしまうことなど予想もしませんでした…。
こうした理由により、私はポスドクを辞めることになりました。
むしろ、辞めなければならない精神状況に追い詰められました。
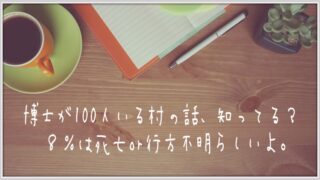
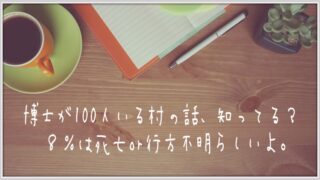
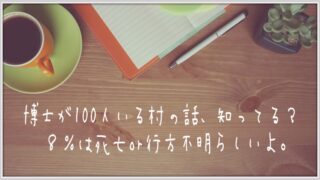
※信ぴょう性はありませんが、無視はできないお話です。
大学院博士・ポスドクを通して得られたもの
約10年間を費やした私の研究生活にどんな意味があったのか。
結論から言えば、研究を通して多くの貴重な経験をすることができ、そして多くの挫折をも経験したことで、私自身がとても成長できたと思います。
研究者って優秀ですよ。
私の持論ですが、大学院生(博士)・研究者は、研究職を辞めたとしても、起業して個人で仕事をする能力がある人がほとんどだと思います。
その理由は『自ら学び、考え、そして行動する』ことができるし、これまでも研究を通して実践してきたことです。
そのスキルのベクトルを研究以外の方向へ向けるだけで、何者にでもなれると確信しています。それだけの”人間力”は自然と養われてきたはず。
そのことに気付いていないだけ。
2018年には「副業が解禁」され、2020年には「個人の時代」と呼ばれるまでになりました。つまり、個人の力が重要とされる時代を私達は生きています。
こうした時代において、『自ら学び、考え、そして行動する』というスキルの重要性に気付けない人は時代の変化に取り残されていきます(20~30代の世代であればなおさらやばいです)。
私が研究を通して得られたものは、幸いにも今の時代に必要不可欠な能力になっているのです(だからこそ、私はまだ生きていけているのかもしれません)。
最後に:博士は研究で培ったスキルをもっと活かすべき
研究職を経験した私から、大学生 or 大学院生への提案があります。
現在、大学院博士課程、もしくはポスドクで研究職を続けていくかを迷っている方であれば、まずは研究を続けながら『起業』or『フリーランス』として活動し始めることで、あなたが抱く将来の悩みを解決できる可能性があります。
つまり、“自分の活躍できる場所を研究職以外にも作り始めましょう”ということ。
特に大学院博士課程にいる学生ではれば、絶対に始めるべきです。
すでにご存知かもしれませんが、個人で『起業』したり『フリーランス』として活動するためのプラットフォームは整っています。
あとはあなたの行動あるのみ!
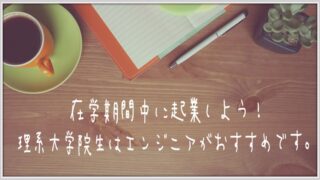
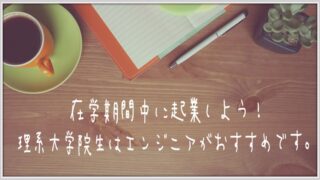
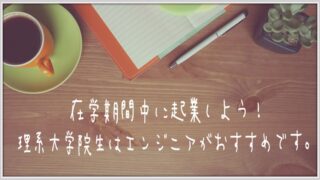
※経済的に自立することは若手研究員にとって重要です。
以上です。
研究がんばってくださいね。